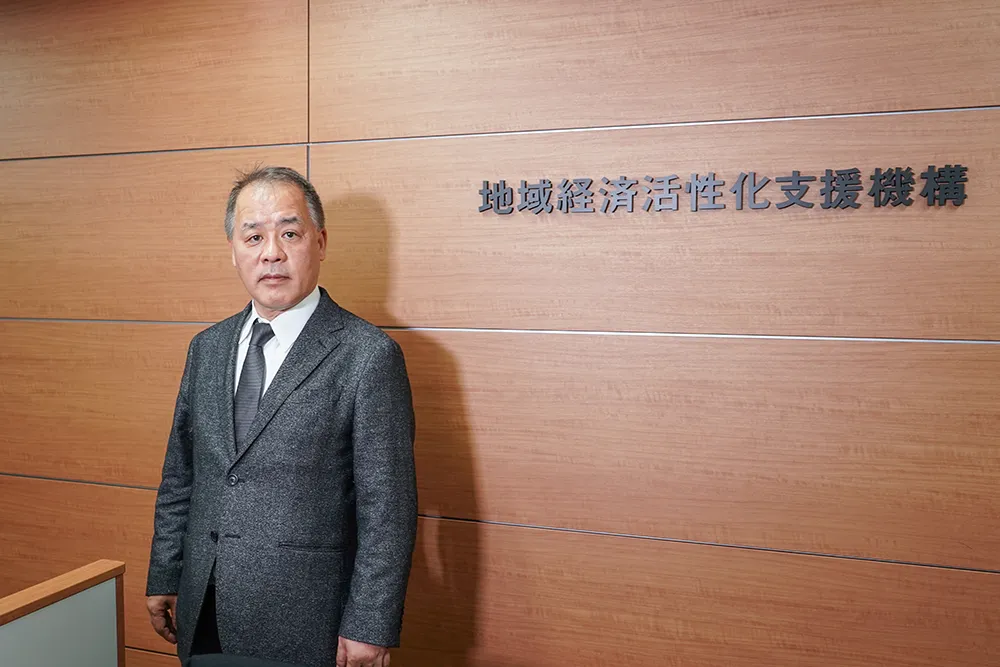
株式会社地域経済活性化支援機構 執行役員 マネージング・ディレクター 兼
株式会社観光産業化投資基盤 代表取締役 大田原博亮 様
次世代を育てずして「ああ、楽しかった」では終われない!地域を動かす人材とは?
地域経済の活性化を目的に、中小企業者等のさまざまなライフステージにおいての支援を、地域の金融機関と二人三脚で行っている株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC:レビック)。その執行役員でマネージング・ディレクターの大田原博亮さんは、ジェムストーン代表高石の元上司。「ビジネスのなんたるかを教えてもらった」と高石がいう大田原さんが日本を支える地域経済をどのように活気づけているのか?またそこに必要人材とは?今後の展開は?などについてお話を伺ってきました。
株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)・株式会社観光産業化投資基盤(TiPC)
株式会社地域経済活性化支援機構は、2008 年秋以降の金融経済情勢の影響から低迷した地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的に制定された「株式会社企業再生支援機構法」に基づき設立された株式会社企業再生支援機構を前身とした機構。時限立法で数回の延長を経て 2030 年が期限。株式会社観光産業化投資基盤は、株式会社地域経済活性化支援機構のファンド運用会社の一つ。観光庁、環境省、文化庁などの関係省庁や地域の金融機関などと共に、観光による地域経済活性化を推進している。

大田原 博亮(おおたはら ひろすけ)
北九州市八幡出身。東京大学法学部卒。国際電信電話(現:KDDI)、PwC(現:IBMコンサルティング)、再生ファンド(エーシーキャピタル)とコンサル会社(コーポレートディレクション)の共同出資会社であるCDI-Sなどを経て、2014年にREVIC入社、rマネージング・ディレクターを務める。
資格取得時に目の当たりにした企業再生の過程
やりたいことが見えた!
—— 東京大学法学部をご卒業後、現在のお仕事に直接関わることではなく、通信系に就職されたのには何かきっかけがおありだったのですか?
大田原氏:本当は外交官になりたかったんですよ。でも、外交官となった大学の先輩たちから、外交官は家柄が大事だ、と聞いて諦め、母方の親戚に通信系の方が多く、馴染みのあった通信系に進みました。さすがに親戚と同じ会社は気が引けてライバル会社でしたが(笑)。
—— 家柄ですか?!
大田原氏:出身が製鉄業で有名な北九州の八幡で、祖父・父とも新日鉄八幡の元請の会社を経営していたので、それなりに恵まれた環境で育ったのですが、製鉄業の衰退と共に、街も会社も寂しい感じになってきていて。国際政治のサークルに所属するなどしていたものの、進路変更しました。
—— その後、コンサルティング会社へ転職されたのはどんな思いがあったのでしょう?
大田原氏:勤めながら自分が会社でやってきたことを体系的に学ぼうと中小企業診断士の資格を習得したのですが、その過程で実習があり、ある美容院を担当しました。そこは多店舗展開していて順調に見えましたが、新しいことに挑戦しない保守的な会社で、過去に不動産投資に失敗して再生が必要な局面であることが実習の過程で明らかになったのです。ここをなんとかしようと懸命に動いている中で、私たちの動きを見て泣いて感謝してくれる老経営者に祖父の姿を重ねたのか、「あー、これが自分がやりたかったことだ」と思えたのです。
資格を取得後すぐ、企業経営の基本でもあるビジネススキルを体系的に身につけるため、当時世界2位だったPwC(入社1年後にはIBMと統合)へ転職しました。
—— そこから実際にいくつかの企業再生に関わられたそうですね。
大田原氏:そうですね、コンサルタントとしてビジネスの基本はわかっても、実際に自分が経営者として関わらないと経営者にアドバイスなんてできないと、経営側から再生に取り組み始めました。
バッグを中心としたアパレル企業や、建設業など、業種はさまざまでしたが、企業経営は"利益・キャッシュの最大化とリスクの最小化"がゴールで、そのための方程式が見えてきたので、どこでも成功できました。
最後は、ファンドとコンサルティング会社が合同で設立した会社で、医療系等の精密機器の大手企業の上場維持のプロジェクトを請け負ったのですが、無事に上場維持できてプロジェクトが成功しても引き止められる状態に「何のためにやっているのか?」と疑問が湧き上がってきたのです。正直答えが見えている方程式をずっとやってもつまらないなと。

寂れていく街、寂しそうな祖父を前に何もできなかった経験が地域活性の道へ後押し
—— そこから地域経済活性化の道へ向かわれたのですか?
大田原氏:はい。以前所属していた大手コンサル会社のOBがREVICにいて、一緒に「地域活性化モデルを作らないか」と誘ってくれたのです。2014年のことです。同時期に他にも海外アパレル企業の転職の誘いはありましたが、地域活性化モデルは何がゴールが分からず、全く成功への方程式が見えないところに強く惹かれて決めました。
—— 実際にREVICに入られてからはどのようなことに取り組まれたのですか?
大田原氏:まずは観光の担当となって、全国の観光地を視察して回りましたね。ほとんどの民間ファンドは投資を行うことを主としていて、地域の実情を把握しきれていないし、自分ごととして変えようとしていない。「それで成功するわけがない」と思っていましたから。
実際に回ってみて、地域の観光産業は一般的な産業と違い、担い手が、自治体の「官」、宿泊・お土産物・交通といった「民」、第三セクターや寺社仏閣などの「公」、銀行などの「金」とあり、これがまたバラバラで、経済的合理性で動くのではなく、感情、好き嫌いで動いていることがわかりました。「あのお店の主人と、あの宿の主人は子どもの時から仲が悪くて、お互いに言うことを聞かない」なんてことが本当にあるんです。
それでも、昔はそれを取りまとめられる地元の有力企業のカリスマ経営者がいたのですが、地方産業が衰退してしまって、それどころではなくなってきている。だから、その代わりとなるまちづくり会社が必要だと実感しました。
このまとめ役だった企業の衰退や、街全体の衰退をみて、昔、自分の会社が衰退し八幡の街が寂れていくのを、寂しそうにみている祖父を前に、何もできなかった中学時代を思い出し、だからこそこれがやりたかったのだと、再生事業や地域活性化事業に関わるようになった源泉を再確認した気がします。
—— 思いを新たにしながら初めに作られたまちづくり会社が信州長野でのプロジェクトとのことですが、具体的にはどのような内容だったのでしょう。
大田原氏:信州湯田中温泉でのプロジェクトです。近くに"スノーモンキー(地獄谷野猿公苑)"といって猿が温泉に入りにくる集客の目玉があるにも関わらず、観光客は東京や長野市などからバスで来て、宿泊せず帰ってしまう状況で、温泉街は休廃業旅館が多く閑散としていました。その再生を目指し地元の地域金融機関からREVICへ支援を求められたのですが、遊休不動産はあるけれどリノベするお金がない、やる気のある若手事業家はいるけれど経営者としての経験はまだ十分でないというのが実情でした。
そこで、観光不動産会社と観光まちづくり会社の2社を、REVICの観光ファンドから、資金と常駐する経営のプロを投入する形で設立しました。不動産会社ではカフェやバーといった夜に楽しめる場を作り"宿泊する魅力"を整備し、まちづくり会社では若手事業家を育てる気持ちで、事業参入へのハードルを低くする仕組みを作りました。
結果、我々が介入した物件以外でも、沿道エリアで観光客の増加を勝機とみて自主的に動いた事業者もいて、エリア全体では4年間で宿泊者が約3倍になりました。
しかし、これは一つの沿道を活性化しただけにすぎず、"地域経済の活性化"ができたかというと、できていなかったと思います。

日本を救うにはより大きな動きが必要
目指したのは官公民金を巻き込んだホールディングスモデル
—— 真に地域経済の活性化を目指して次の行動へ出られたわけですね。
大田原氏:REVICも時限立法の機関ですし、国策としてインバウンドの増加は絶対命題です。観光庁はインバウンドに関し人数目標を持っていますが、観光消費額の目標も持っています。 この目標を(期限内に)達成するには、狭い範囲の活性化を数多く図るのではなく、より大きな経済が動くエリアでの組織づくりが必要であると感じました。経済の活性化=儲かる仕組み作りには組織論が必要不可欠なのにも関わらず、現状の観光地ではすっかり抜け落ちてしまっていたことも問題だと感じていました。
—— それを実行されたのが今現在活動されている高野山プロジェクトですか?
大田原氏:いいえ、まず高知県物部川地域でその仕組みづくりの基礎固めをしました。地銀である四国銀行とREVICが作ったファンドを資本に、県庁の支援を得てまちづくり会社=DMC(Destination Management Company)を作り、そこから出資や契約関係で地元でも比較的大きな企業(観光・一次産業・六次産業など)を傘下におく形でホールディングス化したのです。強力な会社体を作り地域での求心力を持つことで、地域が足並みを揃えることができるわけです。
高知で一定の成果を得た後に、より大きな経済圏の観光地で横展開をするために、新たな全国ファンドとして観光遺産産業化ファンドを作り、阿寒摩周や函館、平泉、などの地域で支援を開始しました。その規模であれば全国に影響力のある大手企業を巻き込んでの事業展開が可能であると思い至りました。そんな時に、タイミングよくTOPPANさんの文化推進事業本部が文化財のデジタルアーカイブを長年やっていることを知り、高野山で一緒にやりましょう、と高野山に繋いで頂き、高野山デジタルミュージアムの開設に繋がりました。
高野山では、高知で築いたフレームをより大きく、高速に作り上げていきました。大手企業(TOPPAN)、地方銀行(紀陽銀行)、通信(NTT西日本)、電鉄(南海電鉄)を中心にDMCをつくり、官(高野町)、公(金剛峯寺・宿坊協会・観光協会)、民(商業事業者)との資本関係や契約関係を基盤に関係を構築していきました。今では、各組織体のトップが定期的に会合を開き、地域戦略を感情論ではなく建設的に議論し、実行に移しています。
当初こそ資本・契約関係で始まりましたが、今では、例えば「宿坊が雇用不足だけど、どうする?」とか「老朽化した施設をどうする?」といったような、信頼関係無くしてはできないようなご相談も各所からいただくようになっています。

日本中でも希少な人材要件
後天性でない素質を重視
—— ところで高石はじめジェムストーンは、どのようにお役に立てたのでしょう?大田原さんのご活躍のお話に聞き入ってしまいましたが。
大田原氏:地域に対してREVICからハンズオンの人的支援をするわけですが、事業運営スキルやマーケティングスキルを持ったいわゆるオペレーション層のマネジメント人材ではなく、一般的な経営マネジメントスキルと我々が求める地域マネジメントスキルを併せ持った人材が必要でした。
しかし、環境の激変やニーズの多様化、グローバル化とニーズや技術の高速化に伴い、経営マネジメントスキルは高度化が必要で日本中で人材不足な上に、トップダウンではなく高度なコミュニケーションスキルを持って地域の人たちと地域戦略を立てられるスキルも持っている人材となると、まぁ滅多にいないのですよ。
とはいえ人は必要なので、プロジェクトマネジメントスキルなどは後からでもついてくると割り切り、コミュニケーション能力が高く、新しい解が即座に出せる"センス"を持っている人を育成する方向にシフトしました。
実は、高石も誘ったのですが断られてしまい(笑)、代わりに人を紹介してもらっています。
—— 何人かはうまくマッチしたと伺っていますが。
大田原氏:他のエージェントにももちろんお願いしましたが、段違いに良い人材を紹介していただきましたね。(補足:ジェムストーン経由でREVICにご入社頂いた方は、観光チーム以外を含めると7名)
特に観光チームに属している人は地方に常駐もしくは半常駐して、実践的な支援(ハンズオン支援)をしていただいています。あらゆるステークホルダーと良好な関係を築き、彼らが持つスキルとネットワークをフル活用し、観光地の魅力向上、訪問者数の増加に寄与されています。
—— 他のエージェントさんとジェムストーンとの決定的な違いはなんでしょうか?
大田原氏:正直、ジェムストーンの正確な事業内容は知らないんですが(笑)。マルチな能力を持った人より、エッジの効いた人を集めているエージェントという印象ですね。我々の場合は事業を前に進め、かつコミュニケーションスキルが突出した人がよかったわけで、そこにうまくハマる人を探してきてもらいました。
—— REVICは2030年、ファンドは2027年での終了が決まっているとのことですが、今後の日本の観光業、ひいては経済にとって重要なことは何だと思われますか?
大田原氏:観光業に関わらず、日本には経営能力のある人材が圧倒的に不足していると思います。組織論で仕組みが作れても、そこを動かせる人材が育たないと意味がありません。この経営人材の体系的な育成は基本的には国の仕事だとは思いますが、私自身も自分のやりたかったことができて「ああ楽しかった」で終わるのではなく、企業再生や地域活性化といった現場でできる限り経営人材の育成に取り組んでいきたいと思います。
—— 最後に、大田原さんが仕事をする上で大切にしていることを教えていただけますか?
大田原氏:コンサル時代から1)スピード、2)ロジック、3)イマジネーションの3つを大事にしています。昔はこの順番で重要さが増す、要はイマジネーションが最も大事、と思っていましたが、インターネットを通じて情報が瞬時に広まる中で、凄いことを考えたとしても同じことを考えつく人が必ずいます。そのため、誰も真似できないほどのスピードで物事を運べるかが重要だと思っています。だから今は、「スピード」こそが最も大事かな、と感じていますね。